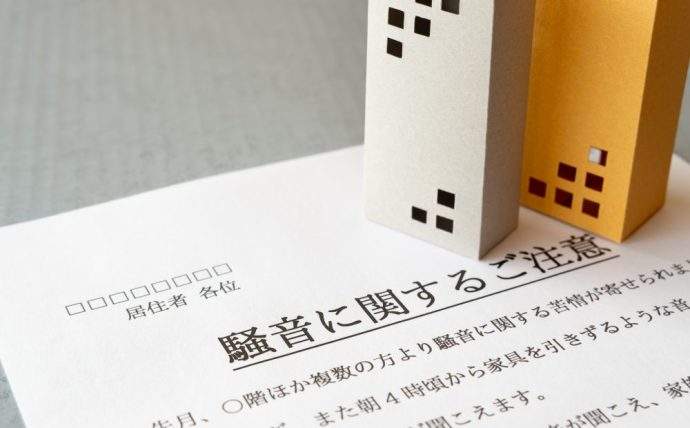家賃滞納への対応手順|注意点や未然に防ぐポイント

家賃滞納とは、あらかじめ決められた支払い期限までに家賃が支払われず、賃料が滞ることです。賃貸経営において大きなリスクとなりますが、よく起こるトラブルでもあります。
入居者が家賃を滞納したときの対応方法には、大きく分けて2通りあります。
● オーナーが自ら対応する
● 管理会社が対応する
管理会社が対応する場合でも、オーナーはひととおりの対応方法は理解しておく必要があります。また、そもそも家賃滞納が発生しないような工夫をしましょう。
家賃滞納への対応手順と注意点を紹介します。
目次
家賃滞納が発生したときにオーナーがすべき対応
家賃滞納への対応は、以下の手順で行います。
- 督促をする
- 督促に応じず支払わないときは文書による請求
- 繰り返し内容証明郵便を送付する
- 裁判による建物の退去・明渡し請求
- 和解と判決そして強制執行
それぞれの具体的な方法を解説します。
督促をする
入居者が家賃の支払いを忘れていたり、自動引き落としの場合は残高不足になっていることを知らなかったりする可能性があります。そのため、家賃が支払われていない事実を告げ、早急に支払いをするよう求めます。
忘れている場合やたまたま残高不足の場合は、速やかに支払われるでしょう。問題なのは支払う資金がないケースです。
この場合、支払いを求めても「○日までに払います」や「少し待ってください」などの答えが返ってくると想定できます。家賃滞納による解約は1カ月の滞納では難しいため、入居者が支払えると言う日まで待つほかに方法はありません。
本来であれば、この時点で連帯保証人に対して家賃の支払い請求をできますが、ケースバイケースです。たとえば、滞納が初めての場合などは、保証人への請求を留保することも多いです。
督促に応じず支払わないときは文書による請求
「○日までに払います」と答えたにも関わらず支払いがない場合は、内容証明郵便で支払督促を行います。
内容証明郵便は後に裁判になったときの証拠になるため、面倒でも必ず文書にするよう心がけます。電話で2度も3度も督促しても、ほとんど効果はないといえるでしょう。
繰り返し内容証明郵便を送付する
滞納分の家賃が支払われないまま月末が到来すると、次月の家賃も滞納になり、2カ月の滞納になります。あるいは、滞納した分が支払われても、再び次月分の家賃が滞納になることもあります。
どちらの場合も、再び内容証明郵便で支払督促を行います。内容証明郵便に付ける配達証明で、居住しているかどうかの確認ができます。ただし、受け取ったとしても、本人が受け取ったかどうかは不明なので注意しましょう。
内容証明郵便が配達されない場合は、転居している可能性もあるため、入居者の部屋を訪問して居住の確認をするのが望ましいです。
裁判による建物の退去・明渡し請求
滞納が続き3カ月分が未納となるころには、裁判の準備を開始します。裁判所へ訴状を提出すると裁判期日が決まるため、指定日時に裁判所に出頭します。
裁判所ヘはオーナー自ら出頭しますが、できない場合は代理人が出頭します。
代理人は基本的に弁護士ですが、訴訟の対象となる賃貸物件価格が140万円以下の場合は司法書士でも代理人になれます。また、管理会社は家賃の支払いや退去に関する交渉は非弁行為になる可能性があり、代理人にはなれないので注意しましょう。
弁護士に依頼する場合、これ以降の手続きはすべて弁護士に委任します。
オーナー自ら裁判所に出頭できる場合は、裁判所に提出する訴状を作成します。しかし、形式が分からない場合は、司法書士に訴状の作成を依頼もできます。
訴状には証拠として、以下の書類も用意します。
● 賃貸借契約書
● 入居者が書いた支払いを約束した覚書など
● 滞納家賃の督促内容証明郵便
和解と判決そして強制執行
裁判期日に相手方の入居者が出頭した場合は、裁判所が和解を薦めて、滞納家賃の支払方法を協議し賃貸借契約を継続するケースもあります。
入居者が出頭しない場合は原告の主張が認められるため、後日判決が出されます。
判決が出た場合は、強制執行の申立に進みます。
強制執行は、「退去・明渡し請求」とは別に申し立てる必要があります。また、退去の際に家財道具が置いたままになる可能性もあるので、残置物の運搬や保管費用を含めた予納金として数十万円がかかります。
家賃滞納の対応で気をつけるべきポイント

入居者が家賃を滞納したときの対応で注意するポイントを紹介します。
感情的にならず冷静に対応する
家賃を滞納されると、オーナーとしては戸惑いや不安、怒りを感じるかもしれません。直接入居者を訪ねて催促や談判になり、感情的なたかぶりからトラブルになるおそれもあります。
管理会社が対応する立場でも、オーナーから強く催促するよう依頼されると、高飛車な態度や言動になるかもしれません。
このような感情的な対応は決してよくありません。冷静沈着に、できるだけ事務的に進めることが重要です。
滞納者との接触は文書のみとし、文面も丁寧かつ誤解を与えることのないよう正確な言葉遣いにしましょう。
内容証明郵便の書き方
督促の内容証明郵便は、文字数と行数に決まりがあります。
内容証明郵便の決まり
| 1行の文字数 | 1枚の行数 | |
| 縦書き | 20文字まで | 26行まで |
| 横書き | 20文字まで | 26行まで |
| 13文字まで | 40行まで | |
| 26文字まで | 20行まで |
参考:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」
注意したいのは、手紙の本文だけではなく、宛名・日付・差出人住所・差出人氏名もすべて上記のルールを適用させる必要があります。
連帯保証人へも同じ対応をする
連帯保証人は、入居者と連帯して家賃の支払いや退去明渡しの義務を負っています。そのため、内容証明郵便の送付や裁判の申立時には、入居者への対応と同時に、連帯保証人へも同じ対応を行う必要があります。
連帯保証人への対応は、法律上で必要というだけではありません。誠実性のある保証人の場合、入居者に代わって裁判外で問題解決に取り組んでくれることもあります。
順調に進むと、強制執行へ進まずに、明渡し退去や部分的な滞納家賃の回収ができる可能性もあります。連帯保証人への法的な対応は意外と効果があるものです。
家賃滞納を防ぐ方法

家賃滞納を防ぐための確実な方法はありません。しかし、できるだけ家賃滞納を発生させないための工夫と、万が一滞納した場合を考慮した事前の対応策を取ることが大切です。
入居審査
家賃の滞納を防ぐには、入居審査で滞納する可能性がある申込みは断ることが最善です。しかし、入居申込者の見きわめは大変難しく、一定のルールを設けることはできません。
そこで、審査時に注意したいポイントを2つ紹介します。
入居申込者が本当に入居する必然性があるのかを申込書から判断する
替え玉申込を見逃さないためにも、申込書をすみずみまで確認しましょう。
替え玉申込とは、真の入居者が現状では無職などのため審査が通らないと考え、知り合いや身内が申し込むケースです。
転居理由や勤務先、家族構成などから、申込者が入居することに不自然さを感じれば、注意しましょう。
インターネットで収集できる情報も重視する
入居申込関係書類だけでなく、申込本人と連帯保証人の両方に関して、インターネットで収集できる情報も重視しましょう。
時間をかけて検索すると、申込者の人柄を把握できる貴重な情報に出会える可能性があります。
家賃債務保証会社の利用
家賃の滞納を防ぐ効果的な方法として、現在では、家賃債務保証会社の利用が一般的になりました。
家賃債務保証は、入居者からの家賃支払いを確実なものにするため、入居者と家賃債務保証会社が保証委託契約を締結する方式です。家賃債務保証の方法には、大きく以下2つがあります。
● 入居者の滞納があった場合、保証会社が代位弁済する
● 入居者が約定日までに、家賃の支払いをする・しないに関わらず保証会社が立替払いをする
入居者が家賃を支払うための口座に関しても、オーナーの口座になるケースと保証会社の口座になるケースがあります。また、保証会社によりさまざまなパターンがあり、比較的審査のゆるい会社と厳しい会社があります。
どの保証会社を使うかはオーナーや管理会社が判断することが多く、入居者が選択するケースはほとんどありません。
家賃滞納などのトラブルも加瀬グループにお任せください!
管理委託の場合、管理会社が以下のような業務をオーナーに代わって行います。
● 入居者募集と契約管理
● 建物管理
● 家賃管理
中でも家賃管理は大変重要な役割であり、その一環として滞納者への対応は最重要な業務といえます。入居審査から月次の家賃収納、そして契約終了時の円満な退去まで、管理会社の対応は、賃貸経営を順調に進めていくうえで欠かせません。
また、前述の家賃保証会社の選択でも、適切な判断が求められます。過去には、家賃保証会社の破たんにより、家賃保証関係の仕組みに混乱が生じたこともあります。
オーナー自身に保証会社を選択するための正確な知見があればよいですが、管理会社の判断に委ねるところが多いでしょう。そのため、管理会社の選択は重要です。
加瀬グループは、アパートなどの賃貸住宅における管理会社としての役割はもちろん、トランクルームやコインパーキング、シェアオフィスなどの幅広い不動産活用のサポートを行っています。そこから得た豊富なノウハウを活用して、家賃滞納の対応だけでなく、クレーム対応や更新手続きなどもすべてお任せいただけます。
まずは、加瀬グループにお気軽にお声がけください。
投稿者

-
加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。
当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。
最新の投稿
- 2026年1月28日土地活用空き家を処分できない!対処方法と確認するポイントを解説
- 2026年1月28日農地農地活用の判断基準|転用のアイデアと使わずに放置するリスク
- 2026年1月16日土地活用空き家の処分方法!売るときの注意点と後悔しないコツを解説
- 2026年1月16日店舗活用ビル経営でよくある5つの失敗例|原因と成功するポイントとは?