駐車場経営でかかる税金一覧|計算例や税金対策も紹介

駐車場経営は、土地活用の中でも初期費用が比較的安価で、経営リスクも低いため始めやすいとされています。
しかし、アパート経営などほかの土地活用と比べると、税制面での優遇措置が少なく税金の負担が大きくなるといわれています。では、駐車場経営にはどのような節税対策があるのでしょうか。
目次
駐車場経営でかかる税金一覧
駐車場経営でかかる税金は、主に以下の7種類です。
■駐車場経営でかかる税金
| 種類 | 課税対象 |
| 固定資産税 | 土地 |
| 都市計画税 | 土地 |
| 所得税 | 所得 |
| 消費税 | 賃料収入 |
| 償却資産税 | 設備 |
| 相続税 | 土地 |
| 個人事業税 | 所得 |
アパート用地や自宅用地の場合は、面積に応じて固定資産税の軽減措置を受けられます。土地にかかる固定資産税が、200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に減額されるのです。
参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
一方、駐車場経営では、固定資産税の軽減措置に該当する敷地ではないため、建物が建っている土地活用と比べると税金が高いのが特徴です。
1.固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋、償却資産の所有者に対して課税される税金です。市区町村によって税率が異なりますが、多くで1.4%とされています。
税金の金額は、固定資産税評価額を基に計算され、計算式は以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額 × 税率1.4%
課税標準額は、固定資産税評価額の70%が目安です。固定資産税評価額は、4月〜5月を目安に市区町村から送られてくる納税通知書で確認できます。
また、前述したとおり、住宅用地の場合は200㎡まで固定資産税評価額が6分の1となる課税標準の特例措置などがありますが、駐車場としての土地活用にはこのような特例措置はありません。
駐車場と住宅用地で固定資産税評価額ごとの固定資産税の目安を比較すると、以下のとおりです。
■駐車場と住宅用地の固定資産税
| 固定資産税評価額 | 駐車場の場合の固定資産税(円) | 住宅用地の場合の固定資産税(円) |
| 100万円 | 1万4,000 | 約2,333 |
| 500万円 | 7万 | 約1万1,666 |
| 1,000万円 | 14万 | 約2万3,333 |
| 3,000万円 | 42万 | 約7万 |
| 5,000万円 | 70万 | 約11万6,666 |
| 1億円 | 140万 | 約23万3,333 |
このように、負担に大きな差があるのがわかります。
2.都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地や家屋、償却資産の所有者に対して課税される税金です。
固定資産税とは違い、市区町村によっては課税されないこともあります。税額は固定資産税評価額をもとに計算され、税率は最大0.3%です。
都市計画税は、以下の計算式で求められます。
都市計画税=課税標準額 × 税率0.3%
都市計画税は固定資産税といっしょに納付します。
参考:総務省「都市計画税」
3.所得税
所得税は、個人が所得を得た場合に課税されます。1月1日から12月31日までの1年間のすべての収入から必要経費を差し引き、所得控除後の課税所得に対して、税率を乗じて税額を算出します。
駐車場経営では、固定資産税や都市計画税、償却資産税などが経費に該当します。
所得税の計算式は、以下のとおりです。
所得税=(所得ー 控除額) × 税率
所得は、収入から経費を差し引いたものですが、自身で駐車場を管理する場合は事業所得または雑所得、管理会社に運営を委託している場合は不動産所得に該当します。
また、税率は課税所得によって異なり、累進課税制度を採用する日本では、所得が多くなるほど税率が高くなります。税率は不動産所得や事業所得だけで決まるのではなく、ほかの給与所得等と合算した総所得によって決まるため、注意が必要です。
総所得にかかる累進課税率は以下のとおりです。
■所得税率と控除額
| 課税される所得金額(課税標準) | 税率(%) | 控除額(円) |
| 195万円以下 | 5 | 0 |
| 195万円超330万円以下 | 10 | 9万7,500 |
| 330万円超695万円以下 | 20 | 42万7,500 |
| 695万円超900万円以下 | 23 | 63万6,000 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33 | 153万6,000 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40 | 279万6,000 |
| 4,000万円超 | 45 | 479万6,000 |
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
4.消費税
消費税とは、商品や製品の販売、サービスの提供などの取引に対して課税される税金のことです。アスファルト造成などの地面の整備がない青空駐車場の場合を除き、駐車場の賃借人からの賃料収入には、消費税が課税されます。
税金の納付は駐車場を運営している事業者が行いますが、負担するのは消費者である賃借人です。
消費税は、以下の計算式で求められます。
消費税=課税取引額 × 税率10%(※2023年7月時点)
なお、消費税の納付義務が生じるのは、課税売上高が年間1,000万円を超える事業者です。駐車場収入とほかの課税売上高の合計が1,000万円を超えない場合には、納税義務はありません。
免税の判定については、国税庁の「売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)」を参考にしましょう。
5.償却資産税
償却資産税とは、駐車場経営で使う設備に対してかかる税金のことです。具体的には、コインパーキングに設置した料金収受機や、車止めなどの機器、舗装、街灯やフェンスなどが税対象となります。
償却資産税には150万円の免税点が設けられており、償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合は課税されません。
償却資産税の計算式は、以下のとおりです。
償却資産税=課税標準額 × 1.4%
課税標準額は、設備ごとに取得価額から一定の算式で計算した償却費を控除して計算するため、償却資産税は年々減少します。
6.相続税
相続税は、亡くなった方の財産を相続した場合に、受け取った財産に課税される税金です。
相続した財産は、経営方式によって国税庁で評価の方法が定められています。
土地所有者が自らアスファルトなどの設備の費用を負担して貸駐車場を運営する場合は、以下のとおりです。
貸駐車場の土地の相続税評価額=自用地評価額
コインパーキングなどの駐車場の設備を賃借人の費用で造成する際は、以下の計算式で評価されます。
貸駐車場の土地の相続税評価額=自用地評価額ー 賃借権価額
相続税評価額の算出方法について詳しく知りたい人は、国税庁「No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価」をご覧ください。
7.個人事業税
個人事業税は、個人が事業を営んだ場合に課税される税金です。事業に対して課税される税金ですが、個人事業税の対象となるかどうかは都道府県が決めます。
個人事業税の対象かどうかの目安は、以下のとおりです。
| 課税対象 | 非課税対象 |
| ● 10台以上の月極駐車場 ● 1台以上のコインパーキング |
10台未満の月極駐車場 |
個人事業税は、以下の計算式で求められます。
個人事業税=(所得ー 控除額) × 税率
税率は個人事業の種類によって異なりますが、駐車場経営の場合は税率5%です。詳しくは、東京都主税局「個人事業税」をご覧ください。
駐車場経営の税金シミュレーション
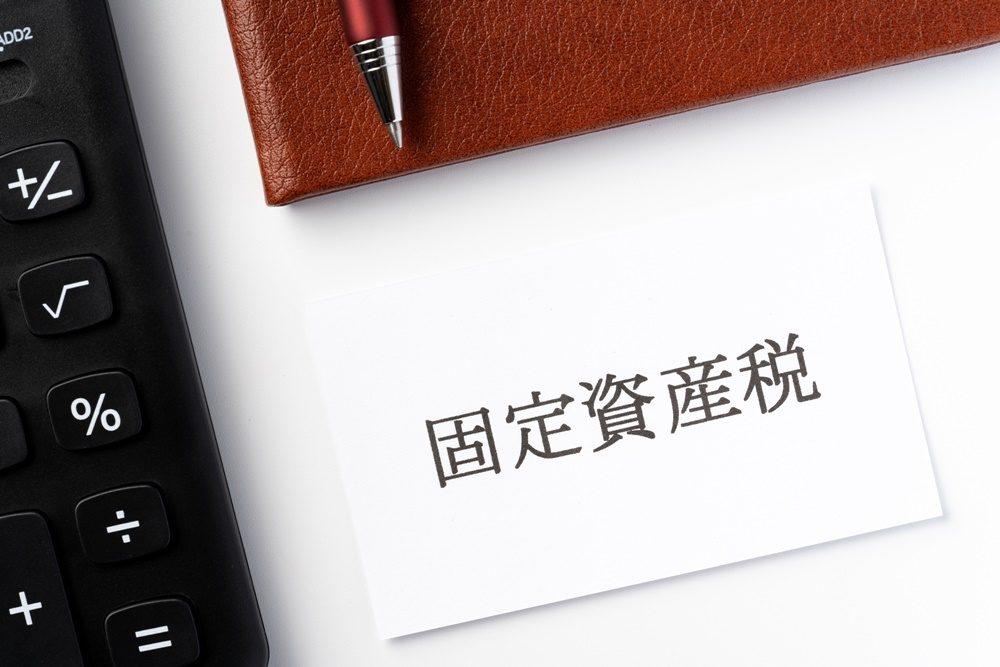
紹介した税金を、月極駐車場を例に計算してみましょう。具体的な条件は以下のとおりです。
【条件】
- 台数:20台
- 年間収入:240万円
- 年間経費:40万円
- 償却資産:50万円
- 敷地面積:350㎡
- 固定資産税評価額:5,000万円
固定資産税と都市計画税は、それぞれ以下のように計算できます。
● 固定資産税:5,000万円 × 1.4%=70万円
● 都市計画税:5,000万円 × 0.3%=15万円
なお、所得税と相続税、個人事業税、償却資産税はほかの課税対象と合算されたり、今回の例では課税対象とならなかったりするため、算出していません。
また、消費税は賃借人が負担する税金のため、反映していません。
駐車場経営で可能な税金対策

駐車場経営では多くの税金が課税されるものの、対策を講じることで節税できます。駐車場経営で節税するための具体的な対策を紹介します。
経費を作って所得税の節税を図る
経費の金額が大きいほど所得は小さくなります。細かな経費をもれなく計上することで節税につながるでしょう。
また、申告方法を工夫することでも節税が可能です。青色申告の承認を受け、帳簿を作成して青色申告特別控除を適用すれば、65万円の控除が受けられます。
住宅用地と一体利用する
駐車場経営を行う土地の隣が自宅や自己所有のアパートマンションの場合は、その建物の駐車場として一体利用することで、住宅用地の特例の適用を受けられる可能性があります。
駐車場の面積と建物のバランスが重要なため、税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
償却資産税が発生しないようにする
先述したとおり、駐車設備の総額が150万円を超えると償却資産税が発生します。特に、500㎡以上の広い土地でコインパーキングとして活用する場合は、償却資産税が発生する可能性があります。
駐車場の設備費の合計が150万円を超えないようにするには、ひとつの敷地で駐車場の種類を分ける方法があります。
たとえば、土地の2分の1をコインパーキングに、残りの2分の1を月極駐車場にすれば、駐車場設備にかかる費用を抑えられます。
駐車設備の総額を150万円以下にできれば、償却資産税は発生しません。
なお、一括借り上げ方式の場合は、管理会社が償却資産税を負担するため、オーナーは気にする必要がありません。
一括償却資産制度を利用する
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の償却資産のことです。通常の減価償却ではなく、3年間で均等に償却できるのが特徴です。
たとえば、15万円の外灯を15個購入した場合は、総額225万円で償却資産税が発生します。しかし、225万円を3年にわたって均等に費用として計上することで、節税が可能です。
参考:国税庁「〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕」
駐車場経営が得意な加瀬グループにご相談ください!
駐車場経営では、さまざまな税金の負担があるため、税金対策を適切に行うべきですが、専門的な知識が求められます。
また、税金対策をしても十分な収入を得られなければ意味がありません。料金設定を誤らないように周辺の相場を調べたり、そもそも需要があるかを把握したりする必要があります。
加瀬グループは、駐車場経営はもちろん、レンタルボックスや資材置き場の経営など、さまざまな不動産活用事業を展開しています。そのため、あらゆる視点からお客様一人ひとりにぴったりの提案が可能です。
駐車場経営を検討するなら、まずは加瀬グループにご相談ください。
関連記事:土地活用で最も無難な選択は駐車場経営?駐車場の利益を最大にする活用法を解説
投稿者

-
加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。
当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。
最新の投稿
- 2026年1月28日土地活用空き家を処分できない!対処方法と確認するポイントを解説
- 2026年1月28日農地農地活用の判断基準|転用のアイデアと使わずに放置するリスク
- 2026年1月16日土地活用空き家の処分方法!売るときの注意点と後悔しないコツを解説
- 2026年1月16日店舗活用ビル経営でよくある5つの失敗例|原因と成功するポイントとは?
















